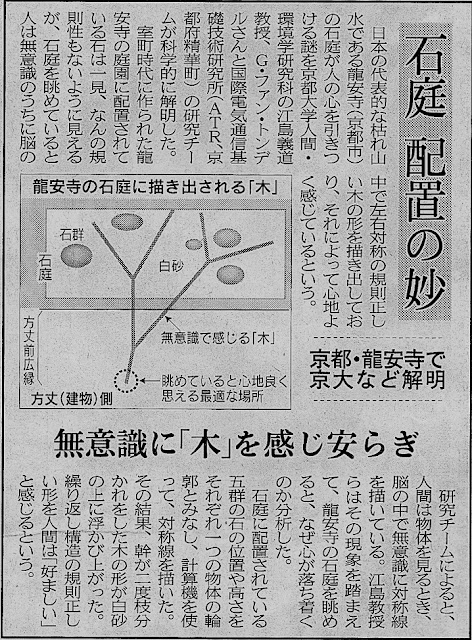2021年12月31日金曜日
死後の行き先 こんな発想も
離れていても変わらぬ思い(感覚)
軟水硬水
2021年12月30日木曜日
”昼夜逆転” そんな理由があったとは
セロトニンを増やす食べ物
勉強になります。 普段から階段を使ったり速足 歩幅を大きくで歩いたり、わざと少し遠回りをしたり、意識しています。 でも改めてスポーツという感じではないので菅、食べる方ならできるかな。というか結構一覧に上がっているものを意識して食べてました。 マイベターハーフ ハニーのためにも赤ちゃん・子どものためにも頑張らなくっちゃ。
2021年12月29日水曜日
2021年12月19日日曜日
「産土笑い」
「産土笑い」もう30年以上も前祖母から初めてこの言葉を教えてもらいました。 すぐ上の子からでも20数年ぶりにこの言葉を思い起こしています。 赤ちゃんはいくら見ていても飽きることはありません。まだこんなに小さいのに色々な表情を見せてくれるなぁ と感心します。 そのたくさんの表情の中でもニコッと笑顔を見せられると「わーっ可愛い⤴」とメロメロ デレデレ です。 その可愛い笑顔 表情を「産土笑い」と言うのだと教えてくれたのです。
赤ちゃんを抱き改めて思うナチスの残忍さ
赤ちゃんは元気です。 よく飲み、運動?手足をバタバタ、抱き上げるとすでに首を支えようとしていると感じるほどです。夜中の授乳は大変ですが、すべてが可愛くてがんばっています。 でも、いくら動きが活発でも寝かされた所からどこかに行くことも食べ物を自分で手に入れることもまだ出来ません。泣き声で人を呼び人にミルクを飲ませてもらい人におむつを替えてもらうしかありません。誰か周りの大人に助けてもらわなければ生きていけません。
改めてナチスの残虐さを覚えます。 ロベルト・ロッセリーニ監督の手による1946年の全6話からなるオムニバス作品「戦火のかなた」の一シーン、ポー川のとてもとても広い河口部、両岸に広がる葦原には水路が走ります。そこを舞台にしたエピソード、後方かく乱の任務を帯びたアメリカ兵と撃墜されたイギリス軍パイロット、そしてパルチザンの人たちが空腹を満たす為その一角にある支持者の一家を訪れる。その後ナチスが襲撃で、その家にいた人たちの中幼児がただ一人だけ生き残り➝わざと殺さず、葦原を走る水路を行き来する小舟が付く桟橋で泣き続けるシーンが出てくるのです。 自分一人では、一口の食べ物も一口の水も、どこかへ行って誰かに助けを求めることも出来ない小さな子だけをほおりだしていく。もちろん殺戮は残虐行為ですが、それ以上に喉が渇きお腹がすきいくら泣いても誰も助けに来てくれない状態で小さな子どもを、じわじわ弱って死んでいく状況で置いていく。 初めて見た時から忘れられない情景でしたが、この度赤ちゃんが与えられ改めて思い起こしました。